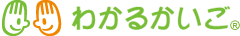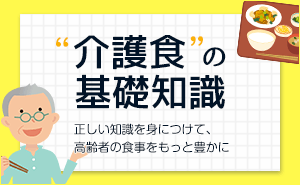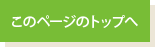パーキンソン病の悪化に関連する因子を発見―東北大学
東北大学の森 悦朗教授(高次機能障害学分野)らのグループは、10月31日、パーキンソン病における認知・運動障害の悪化に関連する予後予測因子を発見したと発表した。
パーキンソン病は運動機能の悪化を主症状とする疾患で、長期経過中に約8割の患者が認知症になることが知られる。しかし、これまでは、後の認知症の発症を予測することは困難であった。
森教授らのグループは、53名の認知症のないパーキンソン病患者に対し、運動機能、認知機能(記憶、視知覚、遂行機能)、FDG-PETで測定した局所ブドウ糖脳代謝の検査を3年の間隔をあけて2回施行し、検査成績の変化について検討した。
すると、初年度に、記憶および視知覚に障害を認めたパーキンソン病患者では、側頭・頭頂・後頭葉の著しい代謝低下が認められ、3年間の症状悪化も重度であることがわかった。
このことは、記憶および視知覚に障害を認めるパーキンソン病患者では、通常考えられていたよりも早い段階で大脳新皮質(側頭・頭頂・後頭葉)に神経変性が起こっており、病状を急速に悪化させる要因になっていることを示唆する。
本研究の結果より、今後、パーキンソン病の予後予測や認知機能障害に対する早期介入に繋がることが期待される。
この研究成果は、10月20日、科学雑誌『PLoS One』(電子版)に掲載されている。

介護の相談を探す

初めての介護
介護へのかかわり方
介護サービスの利用
介護の仕方

介護のキホン

介護シーン別に基礎を知る
みんなが注目する基礎知識